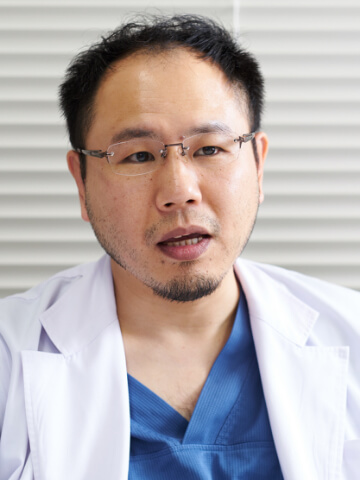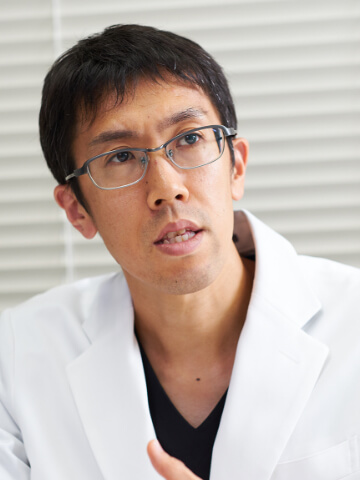院内を変え、市民の
カテーテル治療の最前線を追いかけて
大分県出身の私は、筑波大学附属病院が茨城県にあるということも知らずにやってきました。ただひたすら、カテーテルを学びたいとの思いからです。
医師としてのスタートは脳神経内科で、その後、脳卒中を学びたいと思ったときに大阪で出会ったのが早川幹人先生。内科医としてカテーテル治療をされる姿を見て自分も学びたいと考えました。そして短期留学として派遣された研修先で出会ったのが松丸先生。その後は、故郷の大分に戻る選択肢もあったのですが、もっとカテーテルを学びたいとの志から、「脳卒中科」が立ち上がるという話を聞いて、ぜひ自分も参画したいと考え、場所も知らずに茨城県までやってきたというわけです。
内科と外科の壁を乗り越える
内科医にとって脳卒中というのは、いわばアウエーです。海外では脳卒中患者はまず脳神経内科のドアを叩き、その後、手術が必要ならば外科へと回ります。しかし日本ではそうした連携ができていません。
「脳卒中科」の立ち上げは、従来のそんな壁を取り払うことになる大きなチャレンジでした。もちろん初めてのことでしたから障害はたくさんありましたし、わからないことだらけでした。しかし「1分でも速く治療を」との思いから各方面に働きかけ、意識改革を続けてきました。例えば入院中に脳卒中になる患者さまが多いことから、「すぐにコールを」というステッカーを当院の各所に貼ったところ、今では看護師が「もしや」と思ったらためらわずに私たちに電話をくれるようになりました。
少しずつですが、こんなふうに当院全体の意識が変わってきたのも「脳卒中科」の成果だと自負しています。
子どもたちを通じた啓蒙活動に取り組む
“次は市民の意識を変える番だ”との思いから、現在は啓蒙活動に取り組んでいます。具体的には小学生を対象に脳卒中に関する授業を実施。先生役は救急隊員にお願いすることで、救急隊の意識改革にもつなげています。親は子どもの話には耳を傾けますから、家庭で子どもたちが授業の話をしてくれれば、脳卒中死亡率の高い茨城県の市民の意識も着実に変わっていくことでしょう。
私個人としては「脳卒中科」には内科医の後輩が欲しいと思っていますが、こうした内外への啓蒙活動にもぜひ協力していただけたらと期待しています。

- 日野 天佑Tenyu Hino
- 附属病院 脳神経外科 病院助教
- 出身
- 大分大学医学部 卒業
- 経歴
-
- 国立循環器病センター 脳血管内科 レジデント
- 専門分野
- 神経内科専門医
- 日本脳神経血管内治療学会専門医
- 趣味
- ヨガ、ウイスキー